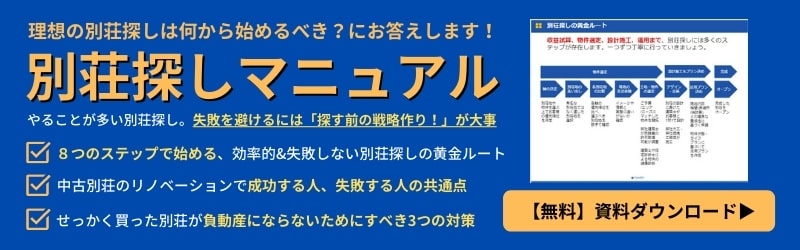別荘にかかる税金は?固定資産税などの種類と優遇措置について解説!

別荘を所有した場合、どんな税金がどれくらいかかるのでしょうか?
本稿では別荘の購入時と所有中、売却時に分けてかかる税金を解説するとともに、セカンドハウスと別荘の違いや優遇措置などについても解説していきます。
別荘とセカンドハウスの違いを理解しておこう

別荘にかかる税金の前に、セカンドハウスとの違いを理解しておきましょう。
別荘とセカンドハウスとでは税金の負担額が変わってくるためです。
別荘とは?
「自宅とは別に住宅を所有する」という点ではセカンドハウスに似ていますが、別荘を所有する目的や利用方法は主に「保養」です。
長期休暇中のんびり過ごして日頃の疲れを癒やしたり、リフレッシュしたり、ゴルフやスキーなどのアクティビティを満喫したりする目的で滞在するのが別荘です。
そのため別荘は「日常生活の用に供しない(日常生活を送る上で“必要”ではない)」という捉え方になります。いわば贅沢品扱いです。
リゾートマンションも別荘と同じくくり?
別荘といえば一戸建てをイメージしますが、リゾートマンションも広義で別荘といえます。
海や山などリゾート地に建っていることが多く、やはり利用の目的は保養がメインとなります。
このためリゾートマンションも別荘と同じくくりと考えてよいでしょう。
セカンドハウスとは?
一方、セカンドハウスとは月1日以上、居住のために利用する住宅です。
たとえば「遠距離通勤者が、会社の近くに住宅を借りて、平日はそこで過ごす」あるいは「毎週末、居住するための住宅」などのことを指します。
こちらは別荘のような贅沢品ではなく住宅というくくりになります。
別荘とセカンドハウスとでは税金面での優遇度合いが異なる
たとえば贅沢品としての別荘と、住宅としてのセカンドハウスいずれも「固定資産税」といった税金はかかります。
ですが目的が異なるため、税制上においても特例措置の適用可否(優遇の度合い)が変わってきます。
当然、日常生活に必要とされるセカンドハウスのほうが、税制面では有利です。
このあと「別荘を購入するときに必要な税金」「別荘を所有している間かかり続ける税金」「別荘を売却するときにかかる可能性がある税金」について解説します。
後半では「セカンドハウスは税金面でどういった優遇措置を受けられるのか」「別荘をセカンドハウスとして認めてもらうことはできるのか」といった疑問にもお答えしていきます。
正しく理解するためにも、まずは両者にこうした違いがあることを覚えておきましょう。
別荘を購入する際にかかる税金

それでは税金について解説していきます。
まずは別荘を購入する際にかかる税金から見ていきましょう。
不動産取得税
土地や建物などの不動産を購入した際に都道府県に納める地方税です。
土地と建物それぞれにかかる税金で「固定資産税評価額×税率4%(令和3年3月31日までに取得した場合は3%)」で計算されます。
購入のほか、譲り受けた場合や新築・増築したときなども課税対象です。
別荘の購入後、半年から1年ほど経った頃に納税通知書が送られてきますので、金融機関で税金を納めます。
登録免許税
中古の別荘を購入した場合は「所有権移転登記」、新築した場合は「所有権保存登記」といった手続きが必要になります。
登録免許税とは、そうした手続きを法務局で行う際に国に支払う税金です。
所有権移転登記を行った場合の税金は「固定資産税評価額×2.0%」で計算されます。
印紙税
別荘の売買契約書を交わす際に必要になるのが印紙税です。税額は、契約書に記載された金額によって次のように異なります。
なお、平成26年4月1日〜令和4年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された金額が10万円を超えるものについては軽減措置が適用されます。
| 契約書に記載された金額 | 印紙税額 | 軽減税率適用後 |
| 10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
消費税
別荘(建物)および不動産業者への仲介手数料などに対してかかってきます。売買契約書取り交わし時点での税率が適用されます。
とにかくやることが多い別荘探しを効率化し、自己利用と収益化を両立する方法はこちら▶
要件整理、エリア選定、物件選定、デザイン間取りの打ち合わせ、施工監理etc とにかく別荘購入には手間がかかります。さらに、それぞれの工程で抑えておくべきポイントは様々です。そこで、別荘を購入するまでの流れを各ポイントごとに「別荘さがしマニュアル」で解説しています。
個人向けに多くの別荘地で、別荘をプロデュースしてきたハウスバードだから分かる、別荘探しのノウハウや落とし穴を解説しています。別荘探しのノウハウをぜひ無料でダウンロードしてご一読ください。
別荘を維持していくためにかかる税金

続いて、別荘を所有している間かかる税金について見ていきましょう。
固定資産税
市区町村に納める地方税で、毎年1月1日時点における別荘の所有者に納税義務が生じます。
土地と建物、それぞれが課税対象で、一括払いと年4回の分納のいずれかを選べます。
ほとんどの市区町村では「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」で計算されますが、固定資産税評価額は3年に1回見直されます。
そのため、長期間別荘を維持している間に税額が変わる場合があります。
基本的には見直しごとに「減価」されていきますが、再開発など何らかの影響で不動産価格が上昇した場合、減価されないこともあります。
また土地の場合は「負担調整措置」がとられる場合があります。
これは、固定資産税評価額が急激に上昇した場合でも、税額の上昇はゆるやかになるよう、徐々に本来の税額に近づけていくという措置です。
※固定資産税の清算について
上述のように、固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に納税義務が生じます。
したがって1月2日以降に購入した場合、本来であれば買い手はその別荘の固定資産税を納める義務はありません。
ですが、不動産売買では「固定資産税の清算」が慣習となっています。
日割り計算し、未経過分を買い手が負担するというものです。
法律で決まっているものではなく、あくまで話し合いで決定されるものですが、購入時にかかる可能性がある税金ですのであわせて覚えておきましょう。
都市計画税
別荘が、都市計画法に基づく市街化区域内にある場合、固定資産税とあわせて都市計画税も納めることとなります。
同じく地方税で、毎年1月1日時点における別荘や土地の所有者が納税者です。
「固定資産税評価額×最高0.3%(制限税率)」で計算されます。
※固定資産税と都市計画税のシミュレーション
別荘と土地の固定資産税評価額がそれぞれ500万円と1,000万円だった場合
- 固定資産税=1,500万円×1.4%=21万円
- 都市計画税=1,500万円×0.3%=4.5万円
上記は別荘と土地の固定資産税評価額がそれぞれ500万円と1,000万円だった場合の例です。
固定資産税と都市計画税の合計25. 5万円を納めることになります。
住民税(市区町村民税・都道府県民税)
市区町村民税と都道府県民税を合わせて住民税と呼んでいます。
別荘がある地域には住民票を移さない、という方が多いかもしれませんね。
ですが、その場合でも一律負担の「均等割」が課されます。
均等割とは、前年の所得などに関わらず、行政サービスを維持するために必要な費用を負担してもらうというものです。
別荘を持つということは、少なからずその地域のライフライン等を使用することになりますので、忘れずに納めましょう。
別荘等所有税(静岡県熱海市)
静岡県熱海市では、昭和51年より別荘等所有税が課税されるようになりました。
これは、別荘やリゾートマンションの増加にともない行政需要(ごみ処理、上下水道整備、救急車の整備など)が増えたことによります。
そうした経費の一部を負担してもらうための税金というわけです。
毎年1月1日時点における所有者が課税対象となります。
税額は1平米につき650円で計算されます。
とにかくやることが多い別荘探しを効率化し、自己利用と収益化を両立する方法はこちら▶
要件整理、エリア選定、物件選定、デザイン間取りの打ち合わせ、施工監理etc とにかく別荘購入には手間がかかります。さらに、それぞれの工程で抑えておくべきポイントは様々です。そこで、別荘を購入するまでの流れを各ポイントごとに「別荘さがしマニュアル」で解説しています。
個人向けに多くの別荘地で、別荘をプロデュースしてきたハウスバードだから分かる、別荘探しのノウハウや落とし穴を解説しています。別荘探しのノウハウをぜひ無料でダウンロードしてご一読ください。
別荘を売却する際にかかる税金

別荘を売却する際にかかることがある税金についても知っておきましょう。
所得税・住民税(譲渡益が発生した場合)
購入時よりも高値で売却でき、かつ諸経費を差し引いても所得(譲渡益)が出た場合、その譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
税率は別荘の所有期間によって次のように変わる
- 長期譲渡所得(5年以上):所得税15%、住民税5%
- 短期譲渡所得(5年未満):所得税30%、住民税9%
所得税や住民税の税率は、このように所有期間によって変動します。
また上記に加え、令和19年12月31日までは復興特別所得税2.1%が加わります。
これは所得税率にかかってくるものです。
トータルすると以下の通りです。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率
- 長期譲渡所得:所得税15%+(所得税15%×2.1%=0.315%)+住民税5%=20.315%
- 短期譲渡所得:所得税30%+(所得税30%×2.1%=0.63%)+住民税9%=39.63%
一方、別荘を売却したことによって「売却損」が発生した場合、これら税金の納税義務は生じません。
とにかくやることが多い別荘探しを効率化し、自己利用と収益化を両立する方法はこちら▶
要件整理、エリア選定、物件選定、デザイン間取りの打ち合わせ、施工監理etc とにかく別荘購入には手間がかかります。さらに、それぞれの工程で抑えておくべきポイントは様々です。そこで、別荘を購入するまでの流れを各ポイントごとに「別荘さがしマニュアル」で解説しています。
個人向けに多くの別荘地で、別荘をプロデュースしてきたハウスバードだから分かる、別荘探しのノウハウや落とし穴を解説しています。別荘探しのノウハウをぜひ無料でダウンロードしてご一読ください。
セカンドハウスは税金面でどのような優遇措置が適用される?

最初にお伝えしたように、セカンドハウスは別荘と異なり税金面で優遇されています。
具体的には「固定資産税の優遇措置」「都市計画税の優遇措置」です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお以下はいずれも令和4年1月時点の情報です。
今後、見直しなどにより変わる可能性があります。
下記とあわせて国税庁のホームページ、あるいは別荘を管轄する自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
固定資産税の優遇措置
- 200平米以下の「小規模住宅用地」:固定資産税評価額の1/6に減額(土地)
- 200平米を超える「住宅用地部分」:固定資産税評価額の1/3に減額(土地)
- 課税床面積120平米までの部分について、新築から3年〜5年にわたって固定資産税評価額の1/2に減税(建物)
※建物は、令和2年3月31日までに新築された別荘が対象です。
※3階以上の耐火構造住宅や準耐火構造住宅は5年間、それ以外の構造は3年間です。
まず固定資産税ですが、セカンドハウスの場合はこのように軽減されます。
都市計画税の優遇措置
- 200平米以下の「小規模住宅用地」:固定資産税評価額の1/3に減額(土地)
- 200平米を超える「住宅用地部分」:固定資産税評価額の2/3に減額(土地)
一方の都市計画税も、このように軽減されます。
セカンドハウスにも住民税はかかる?優遇措置は?
セカンドハウスを所有するということは、別に本宅があるということになります。
たとえば遠距離通勤者の方が会社の近くにセカンドハウスを購入した場合、住民票は本宅を管轄する自治体に登録することがほとんどでしょう。
先ほど「別荘を維持するためにかかる税金」のところでも説明しましたように、たとえ住民票を移していなくても「住民税」はかかります。
均等割と所得割がありますが、別荘と同様にセカンドハウスにも均等割が適用されます。こちらには特に優遇措置はありません。
別荘をセカンドハウスとして認めてもらうことはできる?

仮に別荘をセカンドハウスとして認めてもらうことができたら、税金面での優遇措置が受けられるはずです。
しかしそんなことは可能なのでしょうか?
別荘をセカンドハウスとして認めてもらうには?
- 最低でも月1回以上は帰る(滞在する)必要がある
- 自宅と会社が離れているため、通いやすいように会社の近くに借りた
- 週末に家族で住む場所として購入した など
たとえばこうした住宅は、セカンドハウスとして認められる場合があります。
「日常生活に必要な住居」であることが証明できれば、セカンドハウスとして認めてもらえる可能性があるということです。
立地や利用方法などによっては難しいケースもある
仮に毎月1日以上別荘に滞在したり、家族で毎週末滞在したりしても、必ずセカンドハウスとして認めてもらえるわけではありません。
結局のところ保養目的であったり、会社の近くではなくリゾート地などであったりした場合「生活に必要な住居」であるとは認められにくいためです。
注意!セカンドハウスとしての別荘を取得後60日以内に申請する必要がある
一点、覚えておかなければならない大切なポイントをお伝えします。
別荘がセカンドハウスと認められ、税金の軽減措置を受けたいという場合、取得(購入)から60日以内に「税事務所」に申請する必要があるという点です。
申請方法や必要な書類、要件などは自治体により異なりますので、まずは別荘がある自治体の税務係などへ相談しましょう。
とにかくやることが多い別荘探しを効率化し、自己利用と収益化を両立する方法はこちら▶
要件整理、エリア選定、物件選定、デザイン間取りの打ち合わせ、施工監理etc とにかく別荘購入には手間がかかります。さらに、それぞれの工程で抑えておくべきポイントは様々です。そこで、別荘を購入するまでの流れを各ポイントごとに「別荘さがしマニュアル」で解説しています。
個人向けに多くの別荘地で、別荘をプロデュースしてきたハウスバードだから分かる、別荘探しのノウハウや落とし穴を解説しています。別荘探しのノウハウをぜひ無料でダウンロードしてご一読ください。
かかる税金を正しく把握して楽しい別荘ライフを
別荘を購入したり維持したり、売却したりする際にかかる税金を解説してきました。
いざ購入してから慌てることのないよう、事前にどういった税金や維持費がかかるのかなどはよくシミュレーションしておくことが大切ですね。
使い方によってはセカンドハウスとして認められ、税金の軽減措置が受けられる場合もあります。
本稿が、楽しい別荘ライフを送るための一助になれば幸いです。
別荘の購入は自宅用の物件を購入する場合よりも自由度が高く、様々な要素を選択する必要があります。特に、エリア選定やデザイン間取りの打ち合わせなどには、専門家との視点が必要になります。
参考程度ですが、以下は弊社が別荘を購入検討している方からご相談を受けた内容の一部です。
- 「温泉がある別荘がいいけど、どのぐらい費用がかかるの?」
- 「◯◯万円の予算で考えているけど、別荘は建てられる?」
- 「サウナ作りとかガーデニングとかもしたいけど庭を持てる別荘地はどこ?」
- 「維持管理費用にはどのぐらいかかるの?」
- 「使用しない間に第三者に別荘を貸し出すことってできますか?」
要件整理、エリア選定、物件選定、デザイン間取りの打ち合わせ、施工監理etc とにかく別荘購入には手間がかかります。ハウスバードでは、多くの別荘プロデュースを行ってきたノウハウを元にご相談を受け付けております。「別荘って貸せるの?」「ローンは組めるの?」など簡単な質問からでも受け付けております。ぜひご相談ください。